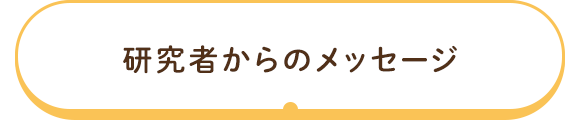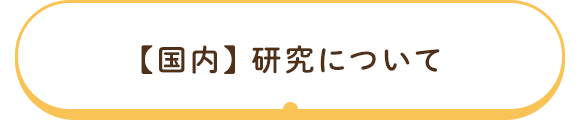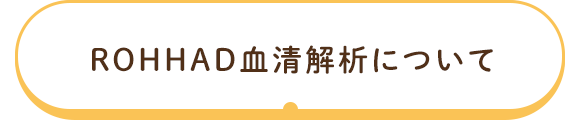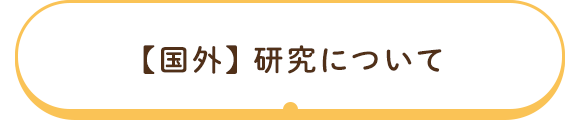研究について
研究者からのメッセージ
慶應義塾大学医学部臨床遺伝学センター 小崎 健次郎 さま 中藤大輔 さま
私たちは現在、ROHHAD症候群を含め、難病に関する研究を進めております。
本研究は、実験を行うものではなく、患者さんの症状や経過を体系的に記録・整理する「レジストリー」の構築を目的としています。
レジストリーを通じて病態を正しく理解することは、将来的な診断や治療法の確立に向けた重要な基盤となります。
ROHHAD症候群はきわめて稀少な疾患であり、未だ不明な点が多く残されています。そのような中で、患者さんお一人おひとりの情報を集め、共通する特徴や課題を明らかにしていくことは、患者さんとご家族にとってより良い医療や支援体制を築くための第一歩となります。
私たちはこの研究を通じて、ROHHAD症候群の理解と患者さんの生活の質の向上につなげていけるよう、全力を尽くしてまいります。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
広島大学大学院医系科学研究科 宇都宮 朱里 さま

ROHHAD症候群に関する自己抗体の研究を行っている広島市立北部医療センター安佐市民病院小児科、広島大学大学院医系科学研究科の宇都宮 朱里(うつのみやあかり)です。
私自身、研究のきっかけとなったのは、原因がわからず、診断がわからない患者さんとの出会いでした。そこから15年以上研究を継続させてもらい、ROHHAD症候群の原因に自己抗体が関連していることや、抗体と症状の程度との関連についてわかってきました。ROHHAD症候群は、稀な疾患といわれているため、医療者側も診断するまでに時間を要することが多くある状況です。現在、より早い段階で診断や適切な治療につながるように、研究開発した抗体検査を広く活用いただけるような体制を立てるべく多くの方にご協力いただき構築中です。
今も症状に悩まれたり、情報が少なく相談窓口がないなど、不安やご心配を感じておられるROHHAD症候群の患者様、ご家族様も大勢おられるかと思います。
ただ、一方で世界や日本国内にいる研究者、医療者の診断や治療に関する進歩が少しづつですが確実に、認められています。また現在も厚労省の研究班や行政の方、検査会社の方などたくさんのご協力をいただき多方面からの応援をいただいています。これからもROHHAD症候群患者さん、そしてご家族皆さんの健康と夢が叶うよう貢献できることを継続していきたいと考えていますので、ぜひ一緒に歩んでいきましょう。
東京医療保健大学立川看護学部 久保 恭子 さま

私は難病児と家族の看護を研究している東京医療保健大学立川看護学部の久保恭子(くぼきょうこ)です。NICU・救命センター・小児病棟・小児訪問看護・小児療育と救急現場から小児医療・保健・福祉分野に長く携わったのち、現在は大学で看護師の育成をしています。
ご縁があって、K君とAちゃんとに出会い、この2人がROHHAD症候群という疾患をもっていました。その後、患者会を通して子どもと出会う機会をいただき、子どもと家族の魅力を感じています。どんな魅力かって?紹介しましょう。
ある時、S君としり取りゲームをしました。S君は「だ」から始まる言葉に「だいすき」を選びました。理由は「いつもママと「だいすき」っていいあっている。1日に何回も言っている」とのこと。なんて素敵な親子でしょう!こんな素敵な日がいつまでも続くように、看護の力も発揮したいと思います。
さて、多くの専門家が子どもと家族の健康や福祉の向上を目指しています。ROHHAD症候群という病気があっても、みんな、大人になっていきます。
合(愛)言葉は「ともだちといっしょにおとなになろう(友達と一緒におとなになろう)」です。人生いろいろあります。
でも、患者会の仲間がいることを忘れないで、みんなで力を合わせて、子どもの素敵な未来のために、ご一緒していきたいと思います。
【国内】研究について
ROHHAD (-NET)症候群における疾患レジストリ作成と血清バイオマーカーを用いた早期診断法、重症度評価法に関する研究
permission.pdf(112K)
情報公開.pdf(203K)
ROHHAD血清解析について
【国外】研究について
ROHHAD症候群は、症例が非常に少なく、国内では小児慢性特定疾病や指定難病認定に至っていません。
しかしながら近年、国内でも研究チームが発足し、研究が進められています。
このような状況から、世界中の医師や研究者が協力し、国際協力が必要とされています。
これらの研究には、各国人種を問わず、世界中の患者が研究に参加することができます。